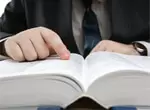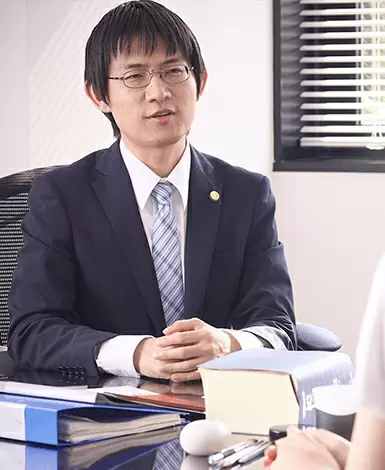65歳未満の障害者特例、長期加入者特例に該当する年金を受給されている方が厚生年金被保険者となった場合の経過措置について
~令和6年10月の社会保険適用拡大に伴って~

令和6年10月1日から社会保険の適用範囲が拡大され、事業所で社会保険に加入すべき労働者の範囲が拡大されました。この適用拡大(令和6年10月1日施行)により、新たに社会保険(厚生年金保険、健康保険)の被保険者となった方が、一定の条件に該当する場合、これまでの制度上では支給停止となる定額部分の年金について、引き続き受給することが出来る旨、厚生労働省から発表がありましたので、ご説明します。
詳しくはhttps://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/leaflet_20241001keikasoti.pdfをご覧ください。
65歳未満の障害者特例とは
60歳から65歳未満の間に受給する年金を「特別支給の老齢厚生年金」といいます。特別支給の老齢厚生年金のうち、報酬比例部分のみを受給している方は、受給者の申請により、申請月の翌月分から報酬比例部分に加え定額部分も受け取ることができます。
- 特別支給の老齢厚生年金の受給権があること
- 厚生年金保険の被保険者でないこと
- 障害等級が3級以上の状態にあること
65歳未満の障害者特例を受給するためには、「厚生年金保険の被保険者ではない」ことが条件となっています。
長期加入者の特例とは
44年以上厚生年金に加入したことによる特別支給の老齢厚生年金を受けている方が、定額部分の受給開始前に、厚生年金被保険者資格を喪失した場合、報酬比例部分だけではなく、定額部分も受け取ることができる、という特例です。
詳しくはhttps://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/2018110702.htmlをご覧ください。
こちらも、障害者特例と同様、長期加入者の特例により定額部分が発生した後に、厚生年金保険に加入し被保険者となった場合、定額部分(加給年金額を含む)の支払いは停止されてしまいます。
令和6年10月 社会保険適用拡大と年金経過措置の概要
令和6年年10月1日から、社会保険の適用拡大(※1)が始まりました。この法改正により新たに厚生年金被保険者になった場合に、これまで受け取っていた「障害者特例による老齢厚生年金」や「長期加入者の特例による老齢厚生年金」は、支給停止されてしまうところでしたが、新たに経過措置が創設され、受給者の申し出(※2)により、支給停止を回避することができる制度ができたということです。
(※1)令和6年10月1日からの社会保険適用拡大の概要
令和6年10月1日からは、従業員数(フルタイムの従業員数+週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数)51人以上の企業において、以下の4つの条件をすべて満たすパート・アルバイト労働者に関しては、社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入が義務付けられた。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
(※2)「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」を提出する必要があります。
ただし、経過措置を受けるためには、以下の条件を満たしていることが必要です。
- 令和6年9月30日以前から障害者・長期加入者の特例に該当する老齢厚生年金を受給していた
- 令和6年9月30日以前から引き続き同一の事業所に使用されている
- 以下の適用拡大に該当することにより、令和6年10月1日(施行日)に厚生年金保険に加入した
【令和6年10月1日 特定適用事業所の企業規模要件の見直しによる資格取得】
特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者は、一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。令和6年10月から特定適用事業所の要件が見直されたことによって、厚生年金保険に加入された短時間労働者の方が対象となります。
<特定適用事業所の要件>
- 変更前:短時間労働者を除く被保険者の総数が、常時100人を超える事業所
- 変更後:短時間労働者を除く被保険者の総数が、常時50人を超える事業所
まとめ
日本年金機構によれば、令和6年11月下旬から、この経過措置の対象となる可能性のある方へ、個別に手続きの案内(郵送)が行われる、とのことです。経過措置の手続きを行うにあたっては、令和6年9月30日以前から引き続き勤務していることの事業主による証明が必要になります。
年金の制度は複雑であり、頻繁に制度が改正されるため、ご自身に影響のあることなのか、影響はないことないのかさえ、理解することが困難であると思われます。年収の壁や社会保険の壁が議論を呼んでいますが、税金や年金に関する情報は、今現在進行中の生活や、老後の生活に直結する、大変重要な内容ですので、法改正には注意が必要です。
専門家のサポートをご検討される事業主の皆様、名古屋総合法律事務所にお気軽にお問合せくださいませ。