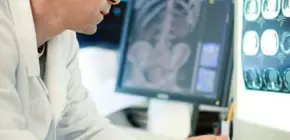弁護士 杉浦 恵一

取締役の任期延長
平成17年に会社法が制定され、もともと商法の中にあった会社に関する規程は会社法に移されました。
もともと取締役の任期は2年でしたが、会社法により非公開会社では取締役の任期を10年まで延長することができるようになりました(会社法332条2項)。
取締役の任期を2年にしていた場合には、2年ごとに取締役を選任(再任)する登記をしなければならず、そのためのコストがかかっていましたが、任期を延ばすことでコストを削減することにつながります。ただし、あまりに改選の時期を先にしますと登記をすること自体を忘れ、過料に処される可能性があります。
取締役の解任
このように取締役の任期を延ばすことで登記をするコストを減らすことが可能にはなりますが、他方で、株主が選任された取締役に不満をもつこともあります。例えば業績不振などで株主が取締役に対して不満を持った場合には、株主は株主総会決議により、取締役を自由に解任することが可能です。
会社法第339条1項では、「役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」と定められています。
いつでも解任できますので時期を問いませんし、解任する条件の定めもなく、理由の制限もありませんので、株主総会の決議さえあれば解任することが可能です。
他方で、選任された取締役としたら、いつでも、理由に制限なく、突然に取締役を解任されると、その後の仕事や生活の問題に関わってくることがあります。
このような解任される取締役の利害関係とのバランスをとるため、会社法第339条2項では、「前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」と定められています。
ここで言う「損害」とは、一般的には取締役を解任されなければ得られたはずの残存任期期間中と任期満了時に得べかりし利益だと解釈されています(大阪高等裁判所 昭和56年1月30日判決)。
解任した場合
このように、取締役の任期を10年まで延ばすことはできますが、途中で解任する場合には残りの期間分の役員報酬等を損害として賠償しなければならないリスクがあります。
しかし、この賠償する期間には上限はないのでしょうか。
会社法上は特に賠償する期間について上限は設けられていませんので、理屈上、条文上は残存期間が長い場合には、かなりの賠償額になる可能性もあります。
この点については、最高裁判所の判断はないようです。
事例
これに類似する論点として、定款変更で取締役の任期を2年以上に延長した後で、更に取締役の任期を短縮することで取締役を退任することになった場合に、このような定款変更が認められるのかどうかが争われた事例がありました。
東京地方裁判所
平成27年6月29日判決の事例では、定款変更によって任期が短縮された場合に、その定款変更により退任することになるか否かという論点について、裁判所は、定款変更が取締役の解任と同様の効果を発生させるものであり、取締役はいつでも株主総会の決議によって解任することができるとされているため、定款変更によって当然に退任させられた取締役の保護は、解任の場合と同様に、損害賠償によって図れば足りるとして、取締役の任期途中でその任期を短縮する旨の定款変更がなされた場合、その変更後の定款は在任中の取締役に対して当然に適用されるとされました。
そのため、定款変更後の任期によれば、既に取締役の任期が満了している取締役については、任期を短縮する定款変更の効力発生時に、取締役から当然に退任するとされています。
そして、任期を短縮する定款変更で退任した取締役にどの程度の損害賠償が認められるかという点では、長期間にわたって会社の経営状況や取締役の職務内容に変化が全くないとは考えがたく、取締役が同じ金額の役員報酬を受領し続けることができたと推認することは困難だということで、その損害額の算定期間は、退任した日の翌日から2年間に限定することが相当だとされました。
このように、残存期間がそれなりにあった場合であっても、上限が2年間に限定されています。
これも最高裁判所の判断ではありませんので、別の争いになれば変わる可能性もありますが、実務上参考になると思われます。
最後に
ちなみに、会社法が制定されたことで有限会社は廃止されましたが、会社法制定の前から有限会社であった会社は、特例有限会社としてそのまま有限会社を名乗ることができ、任期も決めないでいることが可能になっています。
しかし、有限会社の場合には、任期がないことで、取締役が正当な理由なく解任されたとしても、会社法339条2項に基づく損害賠償請求はできないと解されているようです(東京地方裁判所 平成28年6月29日判決)。
このように、会社法の制定により取締役の任期を上限10年にすることができるようになりましたが、途中で退任してほしい場合のリスクもありますので、注意が必要でしょう。